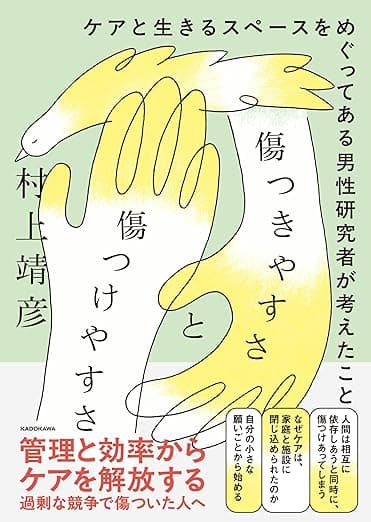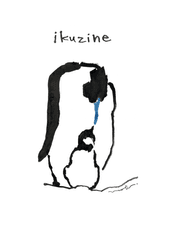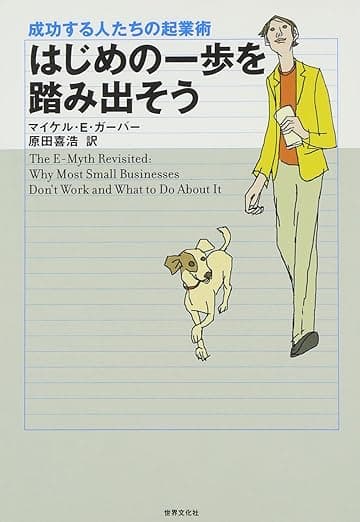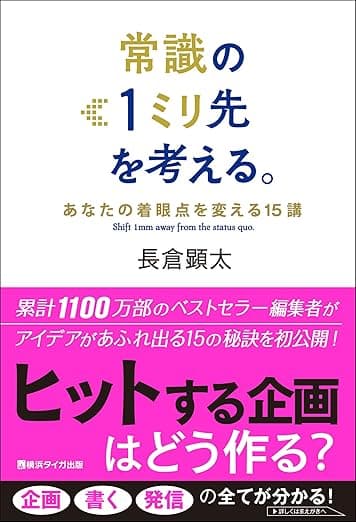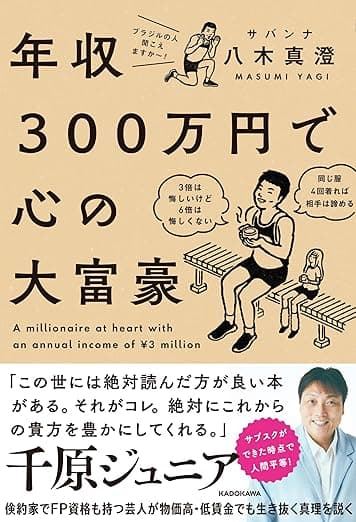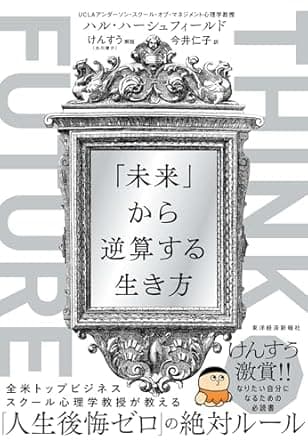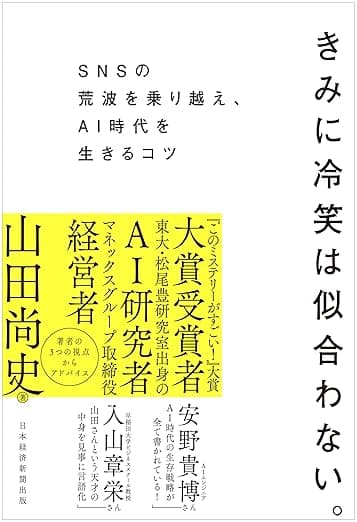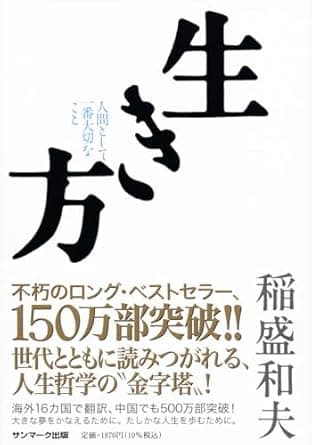「勝負眼」を読んだ
2025/12/11
「勝負眼」を読んだ。サイバーエージェント藤田さんの新作で、週刊文春の人気連載をまとめた形。藤田さんといえば最近社長を交代することを発表して話題となったが、そういう会社の成熟、移り変わりみたいな話題が多い(あと麻雀の話が多い)。
自分が就活の頃、サイバーエージェントはメガベンチャーの代表とされており、説明会や選考にも参加した。他の会社が貸し会議室で説明会を開催するのに対し、サイバーエージェントは大きなホールを貸し切って開催し、最初に藤田さんからのメッセージが巨大モニターに流れる演出をしていた。その当時から藤田さんの見せ方へのこだわりはすごいと思っていたが、本書でもそのあたりは何編か書かれている。
本書で一番印象に残ったのは以下の文節。クールジャパンは日本の文化の良いところを世界に広めようとしているに過ぎない。一方で、クールコリアは自国の文化を世界水準に高めることを目指している。クールジャパンは何か違うなと思っていたが、その理由をズバリ指摘している。今の時代良いものはグローバルで課金される。なのでサービスやプロダクトは世界基準を目指すべきだ。
「歩く マジで人生が変わる習慣」を読んだ
2025/12/01
「歩く マジで人生が変わる習慣」を読んだ。著者はNewsPicksの編集者の方。ある時一足の靴に出会い、歩くのが楽しくて仕方なくなる。これはどういうことなのかとリサーチし、その内容をまとめたのが本書。
この本の存在は以前から知っていたが手が伸びなかった。それは「歩くのが健康に良いこと」はもう知っているから。「脳を鍛えるには運動しかない」や「運動脳」で語られ尽くしている気もしており、新しく知ることはあまりないかもな、と。友人との会話をきっかけに読んでみたところ、半分は前述2冊と重なる内容、半分は新しい内容といった感じで、知らないことも多々あって面白かった。
例えば「歩くと脳がよく動く」というイメージがあったが、これは間違いらしい。そうではなく、現代人の脳は常に動きすぎて疲れている。歩くことで身体優位になり、頭の中が空になる。そうなると適切に余白ができて良い思考ができるという順序らしい。歩くのが思考に良いという意味では一緒だが、このロジックを知っているとちょっと楽しい。
「傷つきやすさと傷つけやすさ」を読んだ
2025/11/22
「傷つきやすさと傷つけやすさ ケアと生きるスペースをめぐってある男性研究者が考えたこと」を読んだ。最近はケアの本をよく読んでいるが、その中でも本書は3本の指に入るくらい面白かった。本屋でたまたま手に取った本なので、出会いに感謝。
まずは冒頭のくだり、「我思う、ゆえに我あり」でお馴染みのデカルトについて。彼は「自己」についての考えを書いていたが、そこには彼の身の回りを世話していた人物への言及がなさすぎることを指摘する。さらにデカルトは貴族の出で受けた教育も良い。特権を享受しつつもそれを自覚せず、あたかも普遍的なもののように表現することはケアを無視しすぎている。この指摘がまず面白い。
そしてケアを無視していることは現代にも通ずる。例えば会社での競争主義は男性が中心となっており、それは家にいる女性にケアを押し付けて成り立ってきたものといえる。自分はいまそれなりに仕事もできて楽しく過ごせているが、それは自分の才能や努力のおかげではなく、そもそも家の中が落ち着いて勉強できる環境で、困ったら塾に通わせてくれる親の考えや投資があり、その結果大学まで何不自由なく進めたことが要因として大きい。しかし気を抜くとそれを忘れてしまう。これはケアにスポットライトが当たりにくい状況を意味する。
「ikuzine」を読んだ
2025/11/19
「ikuzine」を読んだ。その名の通り「育児のZINE」で、著者は友人のヤマダさん。内容はPodcast番組の文字起こしになっていて、参加者それぞれの育児に対する考え方やモヤモヤが読めてとても面白かった。
参加者の中には小説家の滝口悠生さんがいる。滝口さんの表現には心を掴まれることが多かったので書いておきたい。
例えば電車で子供が静かに過ごせたとき、親は「えらかったね」と褒める。しかし静かにしていて嬉しかったのは親目線であって、それを「えらい」と言ってしまうと親の都合すぎるところがある。なので滝口さんは「静かにしてくれて助かりました。感謝してます」と伝える。この表現であれば立場がフラットなまま子供を褒められていて心地よい。
「はじめの一歩を踏み出そう―成功する人たちの起業術」を読んだ
2025/11/11
「はじめの一歩を踏み出そう―成功する人たちの起業術」を読んだ。アメリカでは起業した会社の8割は5年後に姿を消しており、それは共通したとある誤りから来ている。本書では著者のこれまでのコンサルティング経験をベースに、事業がどういう形を目指すべきかを提案する。
いきなり結論だが、事業にとって良い状態とは経営者が「起業家」「マネージャー」「職人」の3つをバランスよく発揮できていることである。起業家の要素がないと夢や志を描けない。マネージャーがないと他人に依存したビジネスになる。職人がないと実践が前に進まない。どのピースが欠けても歯車は狂ってしまう。
自分はエンジニアの歴が長いので、この中だと「職人」の気質が一番近いと思う。職人は自分のスキルを発揮して良いものを作れることに喜びを感じる。しかしその視点は常に下から上を見上げる形で、「作ってから考えよう」となって方向性を誤りがちになる。
ホームランを狙うと空振りしやすくなる
2025/11/10
「常識の1ミリ先を考える」を読んだ。ベストセラーをいくつも手がけた編集者の方の本で、ヒットする企画はどういうものかを15の章に分けて語る。キーワードは「盗んでズラす」。0から生み出すのではなく売れてるものの切り口を変えるのは「コピーキャット」のアイデアの作り方を想起させる。
ヒット作を振り返ってみると、ホームラン狙いのものは失敗しやすいことが分かったという。10万部を狙うぞ、と意気込んだ企画は失敗しやすい。これはホームラインを打つことに意識が行き過ぎて目の前のボール(読者)から目を離してしまうことが原因。著者は読者をひとつ広げてクラスタと呼ぶが、この対象となるクラスタを理解し、その人たちの世界観を分かった上でスイングすると打率があがりやすい。
Webサービスでも同じで、世の中を変えるサービスを作る!と始めてしまうと行き詰まりやすい。規模が大き過ぎてイメージしづらいし、自分の考えたアイデアが世界的に流行るかどうかは企画段階ではわからない。InstagramやAirbnbなどの世界的ヒットサービスも最初は小さく始まっている。その界隈の人に火がつき、少しずつ形を変えながら世界に広がっていった。世界を変えるのは結果であって目的ではない。
「年収300万円で心の大富豪」を読んだ
2025/11/04
「年収300万円で心の大富豪」を読んだ。著者は最近ファイナンシャルプランナー1級を取ったサバンナ八木さん。若手芸人の頃に年収300万でも幸せで、そのヒントとなる考えを紹介していく本。昨日図書館で借りた本はこれです。八木さんは「よしもと営業-1グランプリ」というYouTubeで公開されている番組が面白くて最近ハマっており、その流れで読んだ。人と比べず基準を低く。ジャージ姿でエレベーター乗りづらくなるからタワマンは不要です、とかそういう八木さんのマインドが書かれている。
オードリーの若林さんも春日さんのことを「貧乏な頃から幸せだった」と以前語っていた。若林さんは売れて良いところに住んだり美味しいものを食べたりしても満たされないものがあって、一方春日さんは家賃3万9千円の風呂無しアパートに住んでいるときからずっと幸せそうに毎日過ごしてる。この話はなんだか記憶に残っていてたまに思い返す。
本の中で「勉強はお金のかからない趣味」というフレーズがあった。これはほんとにその通りだと思う。八木さんはFPの本を買って1年間楽しめたと。それに飽きた頃には資格が取れていて、こんなにお得なものはないと書かれていた。プログラミングも無限に遊べる趣味で、最初にパソコンを変えれば後は手を変え品を変えいろんな勉強ができる。うまくいくとお金を稼げることもあるのですごい。絵でも文章でも消費するより自分でそれを作る方が長い時間遊べますね。
「未来から逆算する生き方」を読んだ
2025/11/01
「未来から逆算する生き方」を読んだ。
様々な実験により、「未来の自分」は現在の自分からすると他人のように感じていることが分かっている。例えばダイエット中でもおやつを食べてしまう。これはお腹が出てるのが自分ではなく「未来の自分」だから。
また、未来に想いを馳せるとき、今の自分の延長線として考えることしかできない。情動的なときに考えると未来も情動的だと思う。情動的でない時に未来を考えるとこの先も同じ状態がずっと続くと思う。実際は感情が起伏するので予測とは異なる。
「きみに冷笑は似合わない。」を読んだ。
2025/10/31
「きみに冷笑は似合わない。」を読んだ。副題は「SNSの荒波を乗り越え、AI時代を生きるコツ」となっており、近年のSNSブームやAIによる変化にどう向き合うかが述べられた本。SNSは「何者かになりたい」人々であふれ、「何者かになれた」と自認する人々が自己主張をし、それに対して羨望や嫉妬の声が上がり、簡単に「何者かになる」ための広告が氾濫している。1日あたりのSNS平均時間は143分。食事や風呂など生活の基盤となる営みと同じくらい時間をかけている。それで得られるものは何なのか?「自分も何者かにならなくては」という思いを増長してるだけだとしたら、それは時間の使い方を間違えている気がする。
そもそも「何者かになる」というのはSNSで認められ、注目を集めることではない。それは行動し、実績を積み重ねて見出すもので、本来的には自分がその価値をしっていればそれでよい。世界への貢献やコミュニティへの奉仕の実感が一部の人にしか得られない世の中が、本当に人々を幸福にするのか、私には想像ができない。こちらはAIの進化で「働かなくてよくなった世界」が良いものかを考えた一節。
仕事は対価を得る手段であり、誰かの役に立つ喜びを得られる場所でもある。AIによる自動化とともにベーシックインカム論なども議論されてるが、それが人々が幸せになる未来と結びついてるかは分からない。
少し上の目標に挑む
2025/10/28
入院や手術の話を聞くと身が縮こまる。痛みが苦手、というよりは痛みへの怖れが年々増している気がする。歳を重ねると必ず体調は落ちていくもので、その時が来るのが怖いような気がするが、いろいろ状況も変わるし今から心配するのも違うな。ここでいう状況とは医学の発達とかではなく、周りの友達も同じようにどんどん体が悪くなっていくだろうなということをイメージしている。みんなで渡れば怖くないではないけど、不安や悩みを共有できるのは気持ち的に大きい。
健康の話に比べると、普段悩んでること(「仕事とプライベートのバランス」とか「Webサービスの仕様」とか)は小さな悩みのように思える。健康な体があってどこへでも行ける、これだけで本来はもう100点だ。しかしそれを当たり前と感じているのでさらなる望みを持つ。いい仕事をしたいとか、充実したプライベートを送りたいとか。人間は今ある地点よりも少し上の目標に挑み続ける生き物なのかもしれない。上昇志向を持つのは良いが義務感が出てくると辛そうだ。
京セラ創業者の稲森和夫さんの「生き方」という本に「磨き砂」という考え方が出てくる。自分なりの解釈になるが、人生には苦楽があり、幸せなときと不幸なときと上下する。しかしその都度よく考えて一生懸命取り組むことが大事で、その一連のプロセスが磨き砂となり、自分の魂を洗練させていく、みたいな意味だと理解している。