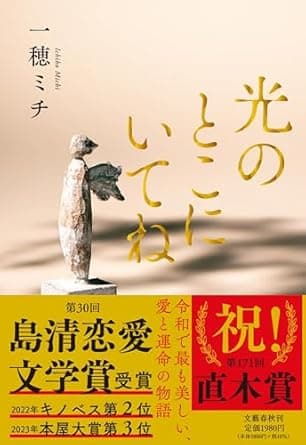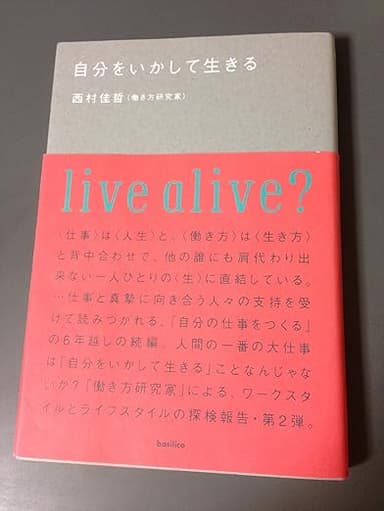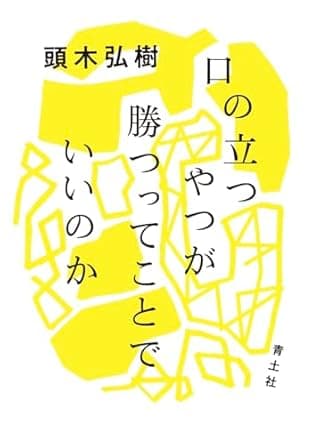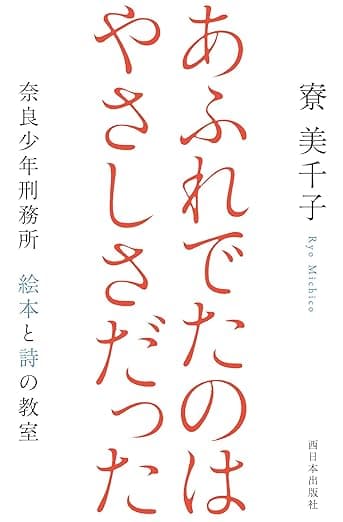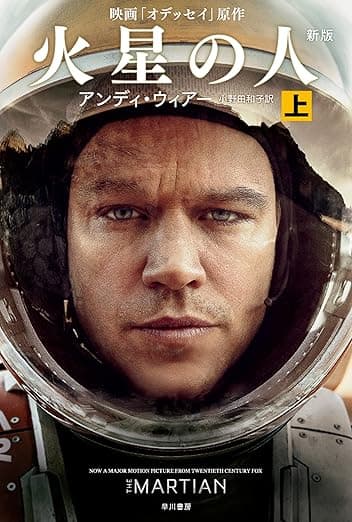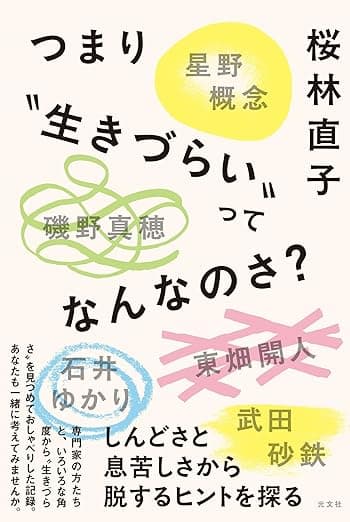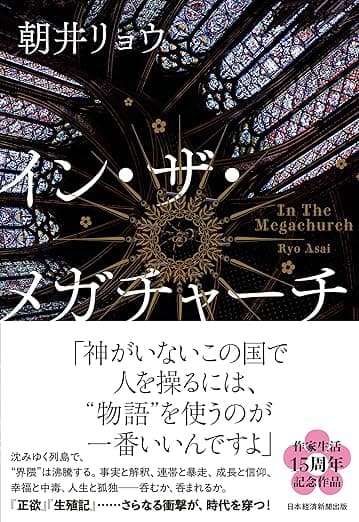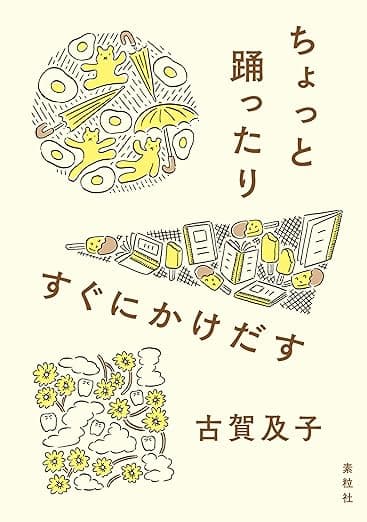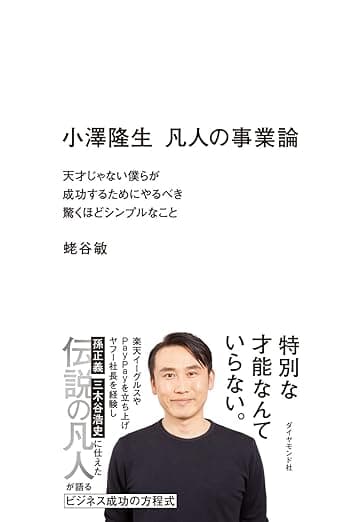余白がありすぎてもよくない
2025/10/18
朝起きて一穂ミチ先生の小説「光のとこにいてね」を読む。一昨日から読み始めたが続きが気になって仕方なく、スキマ時間を見つけては読み進めていた。昼前に読み終わって読後感良し。なんというか良い物語に触れたという気持ちで、充実した時間だった。
朝食を食べて身支度。今日は日中は外に出ようと思っていて、梅田のカフェに行くつもりだったが本を読んでたら遅くなってしまった。今からいくとお昼時と被って入れないかもしれない。色々考えた結果自転車で10分くらいの幹線沿いのカフェに来る。
慣れないカフェに来るとまずメニューにノンカフェインがあるかを探す。いざとなればカフェインを摂取する構えはあるが、体がフラフラになってしまうのでできればノンカフェインが好ましい。ルイボスラテというのがあったのでそれを注文。かなり美味しくてうれしい。
「自分をいかして生きる」を読んだ
2025/10/15
「自分をいかして生きる」を読んだ。著者は働き方研究家の西村さん。以前読んだ「自分の仕事をつくる」では各界の現場を訪ねて「いい仕事」に迫っていったが、本書は対象を仕事から人生に対象を拡げる。
自分を活かす、というとすぐに連想するフレーズは「好きなことを仕事にしよう」。しかしこの表現は実際と少しズレていると著者はいう。その道のプロの現場に足を運んで見る光景は「この仕事が好き」ではすまない態度だったりする。悩み苦み、ただ好きなだけでは潜れない深さまで達している。ではどういう表現だとよいか?それは例えば「あなたが大切にしたいことは?」あるいは「自分がお客さんでいられないことは?」というフレーズである。
自分の場合に置き換えて考えてみると、例えば漫画や音楽は好きだが自分でやろうとは思わない。しかし居酒屋のモバイルオーダーのアプリの出来が悪いと自分で作りたくなる。そんな感じだろうか。でも、これは今エンジニアとしてのキャリアがあるから思うことかもしれない。もっと遡ると大学時代、何かのイベントの進行を見て自分ならもっと上手くやれると感じていた。勝手に改善点を考えたりしていた。こっちの方が原点に近いかもしれない。
「口の立つやつが勝つってことでいいのか」を読んだ
2025/10/14
「口の立つやつが勝つってことでいいのか」を読んだ。Xで話題らしくて本屋に行ってもなかなか出会えず、Amazonでポチってゲットした。エッセイ集だがこれといったテーマがあるわけではない。著者の方が見たこと、気づいたことが言葉で表現されていてとても読み応えがあった。
本書のタイトルにある通り、「口がうまいというのはそんなに良いことなのか?」という点から本書は始まる。ひろゆきが人気を博したように、相手をうまく言いくるめられる人がすごいとされる世界になってきている。しかしテキパキと意見を言うのはそんなに良いことなのか?著者はむしろそれはいかがわしく、口ごもったり迷ってる人の方が温かみがあるという。
自分もお笑いが好きで育ったので、かつてはたくさん喋ったりエピソードトークを淀みなく喋ることがクールだと思っていた。でも最近はちょっと違ってきて、たくさん喋るとそれだけハズレの言葉を選んでしまっている、という感覚がある。例えば「個人開発はお小遣い稼ぎに良い」と発言する。これは正しい側面もあるけど自分の見えてる世界とはかなりズレており、こう表現してしまうことで自分を裏切った気分になる。なので言葉を選ぶようになり喋る時間が短くなってきている。それに伴いテキパキと論理的に喋る人は苦手になり、失敗したり勝ち目のない戦いをするような不合理な人と一緒にいたくなってきている。
「不完全主義」を読んだ
2025/10/13
「不完全主義」を読んだ。放っておくと効率的に、生産的に、完璧にこなそうとしてしまう私たち。しかしそれには際限がなくてやがて疲れてしまう。完璧じゃない自分を受け入れ、その上で大事にしたいことを選んでいきましょう、という本。
著者の前作「限りある時間の使い方」は日本でもヒットして自分も読んだが、これはそんなに刺さらなかった。一言でいうと「タスクをもっと効率的にこなす、という発想をやめましょう」という本で、その考えは少し前から自分のなかにあったからだと思う。今回の不完全主義のテーマは「完璧主義を手放しましょう」。これは自分にとても刺さるメッセージだった。
完璧主義とはどういうことか?例えば街を歩いていてホームレスに小銭を募金しようとする。しかしそこで「いや、支援団体に寄付した方がもっと効果的だと聞いたことがあるな・・」と出しかけた手を引っ込める。そして結局支援団体を探すこともなく終わってしまう。
奈良監獄ミュージアム
2025/10/05
本日は日曜日。週3勤務にしてからは曜日感覚がなくなっていて今日が何曜日なのか分からない。海上自衛隊は曜日感覚を保つために毎週金曜日にカレーを食べるらしいので、それにあやかって今日の夕飯はカレー。デパ地下で買った惣菜のコロッケを乗せてコロッケカレーにしたらめちゃ美味しかった。
旧奈良監獄を星野リゾートが運営することになったらしく、来年ホテルとミュージアムとして活用されるらしい。建築物として素晴らしいのだが保存するだけでは予算が厳しく、活用する形で維持していく試みの第一弾とのこと。奈良監獄とは後の奈良少年刑務所で、奈良少年刑務所といえば「あふれでたのは やさしさだった」で取り上げられた場所である。内容が興味深くて印象にグサリと残っており、いつか訪れて見たいと思っていたが存在を知った時点ですでに閉鎖されていた。それが星野リゾートの元でまた訪れられるようになるらしい。
ミュージアムでの収益をかなり見込んでいるようだが、ホテルにも泊まってみたい。しかし奈良監獄は星野リゾートの最上級格「星のや」らしく、1泊2ケタ万円するため行く機会がまったくない。こういう時はお金がたくさんある方が便利だな・・と思いつつ、持っている制限の中でやりくりするのも普通に楽しいので何が幸せかは分からない。マックで食べるポテトも美味しいし。「経験をお金で買う」の経験のスケールが大きくなることは自分の場合どれくらい幸せに作用するのか。
寝る前にSFを読むと良い
2025/10/02
久しぶりにiPhoneアプリを作っているが、そうなると隙間時間によくスマホを触るようになる。使い勝手やバグなどの検証で触るのだが、そうなると色々アイデアが沸いてくる。若い頃はこうして磨き込みをしていたのがだが、今これをずっとやってると何だかしんどくなってきた。やることが山積みでプレッシャーもあり、頭のなかの余白が潰されていく感覚がある。明日はノーパソコンデーとして、スマホからもそのアプリは消しておくことにした。ゆっくり映画でも観ることにする。
家に届いていた書類を記入してポストに投函。iDecoの書類で、フリーランスになったので枠が増えたり銀行を登録したりと諸手続きが必要になっていた。こういう手続き系の仕事をミスらないのが今年の目標なので早めに提出。あとはGoogleの登録情報が古くて広告収入を受け取れなくなっていたのも修正。表示されるエラーメッセージが実態と異なっていてドツボにハマっていたが、担当の方にメールで問い合わせたら一発で解決した。2戦2勝。
前髪が伸びてきてストレスフルになってきている。次はパーマを当てたいと思っているが、いつもパーマの時に音がいしていた東京の美容師さんが退職されたので行くアテがない。家の近くで見つけたいが美容院でじっとしてるのが苦手なので適切な場所を探すのに腰が重い。ほとんど誰に会うでもないので何でもいいのだけど、お金を追加で払って納得いかないパーマを当てられてしまう理不尽さを恐れている。
「つまり”生きづらい”ってなんなのさ?」を読んだ
2025/09/23
昨日から体が熱い。熱を測ったら微熱だったけど手のひらや足裏が熱い気がする。調べてみるとストレスや自律神経の影響が考えられるとあり、この2つは大体どんな症状を調べても出てくるな。涼しくなってきたので今日はどこか出かけようと思っていたが断念して自宅で過ごす。夕方の明るい時間からぬるめのお風呂に入る予定。
「つまり”生きづらい”ってなんなのさ?」を読んだ。「生きづらさ」をテーマに著者の桜林さんが5人の専門家の方と対談したものを記録した本。友人のPodcastでタイトルが出てきて気になって購入したが面白かった。
ひとことに生きづらいといっても色んな生きづらさがある。学校や会社に馴染めなくて生きづらい人もいれば、そこに合わせるのが上手すぎて自分を歪めてしまい生きづらい人もいる。なので「生きづらい」人たちで集まっても事情がみんな違うので解決に繋がることは少ない。自分は何を辛く思ってるのだろうか?
「イン・ザ・メガチャーチ」を読んだ
2025/09/21
朝井リョウさんの新刊「イン・ザ・メガチャーチ」を読んだ。帯にある「神がいないこの国で人を操るには、“物語”を使うのが一番いいんですよ」この言葉に惹かれて本屋で購入。寝る前に少しずつ読もうと思っていたが面白すぎて一気に読んでしまった。
小説のテーマとしては「物語」「ファンダム経済」「視野」などが中心で、3人の人物の目線でストーリーが進行して交わっていく。ファンダム経済という言葉は初めて聞いたが、ググったところ「熱狂的なファンの集まりが生み出す新しい経済圏」らしい。推し活とか投げ銭とか、そのあたりの世界を括るとファンダム経済となる。
ストーリー全体もすこぶる面白いが細部の描写がグサグサ刺さる。「MBTI診断」「アイドルオーディション番組」「陰謀論」「多様性」「仕事とケア」など、ここ数年で盛り上がったテーマが解像度高く描かれている。一人の人間として生きながらこんなに複数の人格の詳細を表現できるものかと驚かされる。物語を使って商品を売り込む人、それに共感させられハマらされる人。どちらにも言い分があり正義がある。
「ちょっと踊ったりすぐにかけだす」を読んだ
2025/09/20
「ちょっと踊ったりすぐにかけだす」を読んだ。著者はデイリーポータルZでライターをされている方で、子どもたちとの3人暮らしの様子を綴ったウェブ日記を書籍化したもの。最近はエッセイや日記にハマっておりいろいろ読んでいたけどこれは抜群に面白い。読み終わるのがもったいなくて1ページずつ大事に読んでいたがついに読み終わった。
この本で書かれてるのは何か巨大なものを作り上げた経験だったり、人生で一度しかないような珍しい体験ではない。もっと毎日に現れる些細なもの。それを喜んだり悲しんだり慈しんだりしながら書き留める。まさに「日記」という感じで、読んだ後には会ったことのない娘さんや息子さんに親近感を覚えてしまう。
自分も毎日こうして日記を書いているけど、古賀さんの文章は一人称で書かれているのがすごいと思う。例えば自分の文章には「〜と言われている」とか「多くの人が〜している」みたいな俯瞰が入り混ぜになってたりして自分の心情にフォーカスしきれていない。古賀さんは思ったことをそのまま書き、すごいと思ったらすごいと言う。人の生活をのぞき見しているような気持ちになる。日常の些細な心の動いた瞬間を書く。読んでいると自分の毎日にも気づかないだけでこういう瞬間があるなぁと気づけるようになる。
「流行りそう」では作らない
2025/09/16
三連休はほとんどパソコンに触らず本を読んだりして過ごしていて、自分の中のものづくり欲が枯れてしまったのかと心配になったが朝にプログラミングを少しするともっと続きをやりたくなり平常運転に戻った。やる気が起きて動くのではなく動くからやる気が出る、というのは真実。今日は仕事の日なので途中で中断し、夕方退勤後にまた続きのソースコードを書いた。
最近は「AI時代の開発組織」とか「AI時代の学習」とか、AIそのものよりひとつ大きな括りの話をよく見聞きする。AI開発への驚きを一通りみな表明したので次のステージに移ったのかもしれない。自分は変わらずAIアプリケーションの可能性を信じていて、AIで面倒なことが楽になったり日常が楽しくなったり、そういうユーザー向けの何かを作ることに興味がある。技術面や組織でのAI運用に比べると日本ではあまり盛り上がってない気もするが、直接的に生活をよくするポテンシャルがAIアプリにはあると思う。
社会人になってから15年くらい個人開発をしていて、いろいろ好きに作ってきた。次は何を作ろうかというのも常に考えている。日常の課題から考えることが多いが、それは数年後に見返すとまったく使わなくなってたりする。その時々で直面する課題は変わる。例えば昔は「位置と連動するリマインダーアプリ」を作りたかった。コンビニに近づくと「牛乳を買う」、ポストに近づくと「封筒を投函する」みたいに通知してくれるもの。しかし今は家で仕事をしているのでまったくいらない。昔より行動がゆっくりになったからか忘れ物も少なくなっている。こうやって輝きがしぼんでいったアイデアがいくつもある。その代わり今気になる別の問題、面倒なことをアイデアメモに追加している。