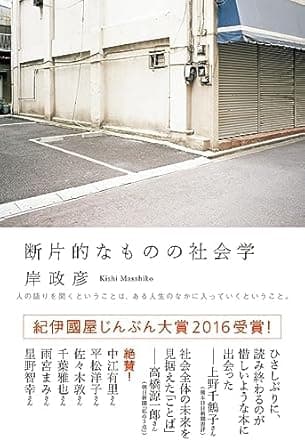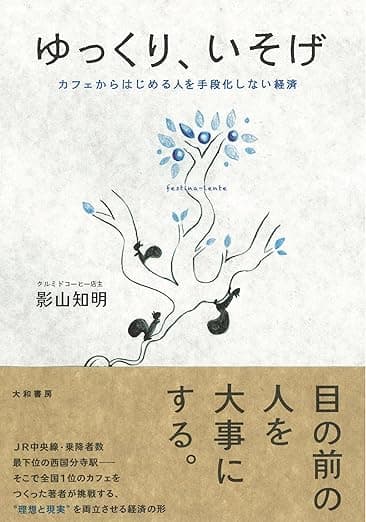「断片的なものの社会学」を読んだ
2025/09/15
「断片的なものの社会学」を読んだ。著者は社会学者の方でいろんな人の話を聞いて調査している。この本は「断片的」で、聞いた話をまとめて意味を見出したりはせず、ただいろんな人の話が綴られている。街を歩いてすれ違う人たちがどんな人生を送っているのか?想像力を働かすきっかけになる一冊。
紹介されている話はどれも自分の世界を広げてくれるものだが、やはり自分と重なるものが多い章には心が動かされる。例えば現代では何を言っても誰かを傷つけてしまう可能性がある話。「結婚して子供も産まれ、幸せに暮らしています」という語りには結婚や子供を持たない人は幸せになれないという含みがあり、それが誰かを傷つけたり焦らせたりしてしまう。これに対して著者はこう書いている。ある人が良いと思っていることが、また別のある人びとにとっては暴力として働いてしまうのはなぜかというと、それが語られるとき、徹底的に個人的な、「<私は>これが良いと思う」という語り方ではなく、「それは良いものだ。なぜなら、それは<一般的に>良いとされているからだ」という語り方になっているからだ。
(中略)
「ゆっくり、いそげ」を読んだ
2025/09/09
「ゆっくり、いそげ」を読んだ。東京は西国分寺駅にあるカフェ「クルミドコーヒー」の店主の方が書かれた本。最近は資本主義の忙しさにストップをかけ、スローペース・マイペースで日々を過ごしたいと思っており、このタイトルが本屋で目にとまって購入した。
著者の方は東大卒、マッキンゼー、ベンチャーキャピタルと経歴を重ねられておりビジネスマンとしても超優秀。資本主義に乗って加速し続けることはやめ、ビジネスとスローライフの中間を目指す。そしてその中間が現実的に可能であることをカフェの営みを通じて理解していく。
例えば「お客さんの消費者的な面」のスイッチを押さない。集客のために広告を出したり20%オフにしたりをやらない。こういう施策は一時的に人を呼ぶかもしれないが、値引きされていない時期を損だと感じ、安く買えた方が良いという思考に一票を入れてしまう。
未来の24時間を考える
2025/09/04
坂口恭平さん著の「生きのびるための事務」の中に「未来の現実を考える」という章がある。今日読み返してみて面白かったので書かれている通りに自分でも試してみた。やり方はとても簡単で誰でもできる。
まず紙に大きく円を書き、現在の24時間の過ごし方をプロットする。7:00-8:00は朝食、8:00-9:00はダラダラ過ごしてそこから仕事、12:00から昼食で...という感じ。1日にかかるお金も書く。こうして今の現実を具体的に書き起こす。自分の場合は業務委託として働いている月火水と、個人開発デーの木金でけっこう違うので2パターン書いた。
次に「未来の24時間」をプロットする。10年後の自分はどういう時間を過ごしていたいか。起きるのは変わらず7:00でいいかとか、朝は散歩したいとか、仕事は15時頃に終えて夕方は本読んだり絵描いたりして過ごしたいなぁとか、想像しながら書いていく。こうしていくと10年後の自分がどう過ごしてるかが具体的になる。あとはその理想通りに時間を過ごしていけば、未来は手元に手繰り寄せられるという寸法だ。
自分がなれない姿に憧れる
2025/09/02
「アンビシャス 北海道にボールパークを創った男たち」を読んでいる。鈴木忠平さんの本は「いまだ成らず」「嫌われた監督」に次いで3冊目。この方の文章はハズレなし。今回もプロローグの数ページを読んだだけで一気に引き込まれてしまった。
テーマは日本ハムファイターズの本拠地移転。球団、オーナー企業、役所、etc... この大事業に関わった人たちに焦点を当てる。個人的には野球にほとんど興味がなく、プロ野球もメジャーリーグも見ずに生きてきたが、それでもこの本は面白い。北海道に行ったらボールパークに行ってみたいとも思っている。野球がテーマではあるが、調整の進め方や熱意を持った提案など自分の仕事に通ずるものもある。
昔ヤフーの社長と話したとき「大きなことを成し遂げたいなら他人を動かす力を、自分のサービスを作りたいなら技術力を身につけたらいい」と言われたことを思い出す。その時は自分のサービスですかぇと曖昧な返事をしたが、アンビシャスに出てくる人たちは前者に近い。球団や市役所などで成果を挙げ、責任あるポジションに着いた人たちが大きな構想を実現させていく。これは個人開発では到底辿り着けない領域。尊敬しかない。
『「みんなの学校」が教えてくれたこと』を読んだ
2025/08/26
『「みんなの学校」が教えてくれたこと』を読んだ。この小学校は大阪に実際にある。そこでは障害のある子もない子も同じ教室で学び、他の小学校で厄介者扱いされていた子も毎日学校に通う。ノンフィクション映画としてもヒットしたらしい。この本はその小学校の初代校長によるもので、大人にとっても大事なことがたくさん書かれていた。
例えば新しい子が転校してくるとき。引き継ぎ情報のようなものは来るがそれを鵜呑みにはしない。それはあくまで前の学校の見立てだとし、先入観なくその子供を自分たちでよく見る。何か問題があったらそれにどう対応すべきか教員みんなで話し合う。大空小学校にはルールはなく、校則は「自分がされていやなことは人にしない」という一つだけ。なので「ルールだから」という呪文は使えず、大人も子供も自分たちで考えて作っていかないといけない。
子供がこの唯一の校則を破ったとき、校長室に来てやりなおしの時間を持つ。やりなおしとは校長先生と話して自分なりにその出来事を理解すること。例えばケンカをして相手を叩いてしまったとする。そうしたら「なんで叩いたの?」「どういう気持ちになった?」「なんで怒ってるの?」などと聞いて自分の感情を振り返る対話が始まる。大事なのは先生側が最後に「よくわかったね。次からはもうしないように」などと言わないこと。この一言があると主従関係が見えてしまう。子供がただ学び、大人はその補助をするくらいでちょうどいい。
「成長疲労社会への処方箋」を読んだ
2025/08/23
「成長疲労社会への処方箋」を読んだ。資本主義のベースには競争があり、競争社会では人々が「もっともっと」と上を目指していく暗黙のルールがある。メンタルを崩す人や過労死はその成長社会の反動として現れている。最近は競争や生産性とは違う軸で物事を見たいなという思いがあり本書もその一環で手に取った。これがとても面白くて一気に読み終わった。
現代は能力主義だが、現代の指す「能力」はとても狭義で、効率や生産性などの向上、つまり効果的にお金を生み出すスキルを指すようになっている。本来人が持つ能力は多種多様、それぞれの人がもつ想像性や創造性が発揮されるだけで十分素晴らしい。それがひとつやふたつの軸に無理やり押し込まれて評価される。客観的な評価にするには定量的じゃないといけない。なので定量で表現できない部分はなかったことにされてしまう。その結果本来違う特徴をもつ人々が同じような人間に整形されて歪みが出る。
次に成長についてだが、これは自分にとって一番面白かった章。何か辛いことがあると最初はそれに苦しむことになる。痛みが大きい間はひたすら治癒するしかないが、ある程度回復してくるとその痛みを自分のギフトだと捉えられるようになる。つまりその体験の表面にあるネガティブな要素だけじゃなく、ポジティブな面を見つけてそれを自分の経験だと思えるようになる。R-指定もラップスタア誕生の中で同じようなことを言っていた。ここまではそれなりに聞く話かなと思う。
「やりきる意思決定」を読んだ
2025/08/17
「やりきる意思決定」を読んだ。プロダクトマネージャーの仕事で一番新しく学ぶ必要があったのが意思決定で、書籍や実際の経験から学んだ内容をnoteにまとめたりしていた。この本はそれを見かけた著者の方から献本いただいた。一冊通して読んでみて、AI時代に人間がやるのは意思決定になるよなぁと改めて実感することになった。
生成AIの性能は本当にすごくて驚かされっぱなしだが、それでも会社や事業をどうしていくべきかを答えることはできない。そのビジョンは人間が決めることだから。ビジョンを実現するための選択肢やヒントを与えてもらうことはできる。しかしヒントのどこを実際に取り入れるか、どう試していくはやはり人間の仕事のままである。
良い意思決定とはどういうものか?情報が適切に集められて、その中から重要なものを精査できて、小さく実践して解像度をあげていく。チームや組織で取り組む場合にはコミュニケーションも重要。意思決定の前提や、なぜその考えに至ったかの文脈を伝えて組織が同じ方向を向ければ推進力が大きくなる。そういった各ポイントについて、本書では具体例を交えながら分かりやすく紹介されている。
「ゆるストイック」を読んだ
2025/08/06
「ゆるストイック」を読んだ。本屋さんでいまの売れ筋としてよく紹介されていたが、紹介されすぎて逆に手に取らず敬遠していた。何かの書籍かブログで言及されていて興味を持ち購入。読んでみるととても面白い。ここ数年で自分が読書したり文章を書いたりしながら考えていたことが言語化されて一冊にまとまっているという感覚で、パラレルワールドの自分が書いたのかと錯覚するほどであった。
まず表題の「ゆるストイック」は「競争にとらわれすぎず、かといって怠惰でもないスタイル」を指す造語。Z世代よろしく最近の若者は競わない。それは他と比べて上にいくことの無意味さを感じているからだが、この競わない性質は「頑張らなくていい」とはまた意味合いが違う。彼らも本当は頑張りたいし、何かに打ち込みたい。ならば競争ではなく没頭を目指そう。自分のやるべきことを明確にしつつ、そのスタイルを周囲には押し付けない、それがゆるストイック式。
自分がエネルギーを注ぐ領域はどう見つければいいか?それは自分の得意なことから探す。自分ではなんとも思ってないことで周りからすごいと褒められた経験を思い返してみよう。他人にとっては大変だけど自分にとっては余裕なことがあれば、それは特技といえる。得意領域を見つけたらそこで継続して頑張ってみる。続けるのが辛いと思わないだけで、そこでは実績を積み上げやすくなる。
「疲労社会」を読んだ
2025/08/03
「疲労社会」を読んだ。スキルや成果を競い合う現代社会、私たちは疲れている。最近はさらにAIが登場し、日々の生産性をさらに高めることを求められる。その疲れの根本はどこにあるか?それは意外にも現代で良いとされる「主体性」「自由」にある。
規律を定めてそこからはみ出すものを罰する社会から、いまは自律性を重んじて高め合う社会になっている。他人に怒られて気を病むのではない。できない自分を自分自身が追い詰めてしまう。そしてそれは自由を与えられ、他者や過去の自分と競い続ける構造に捉われている。
他人から与えられた仕事なら、それを上手くこなせば褒められて一定の満足が得られる。自分で追い求める仕事は、成果が出たら次はもっと上手くやろうとさらに上を求める。この欲求には際限がない。その結果無限に自分からエネルギーを搾取することとなり、疲れ果ててバーンアウトしてしまう。人は活動的になればなるほど、それだけいっそう自由であるというのは、ひとつの幻想であろう。いろんな場所に行っていろんな人と会う。活動的なことは基本良いものとされているが、受けたインプットをそのまますべて表現してしまうとエネルギーが消耗されすぎてしまう。自分のフィルターを通して選別する。良い刺激は受け入れ悪い刺激は無視する。自分の中のブレーキを育てることが本当の自由に繋がっていく。マルチタスクは、後期近代の労働社会および情報社会に生きる人間だけに可能な能力ではない。むしろそれは退化である。
歩くのに飽きた人が踊り出す
2025/07/30
「疲労社会」を読んでいる。競争主義、生産性主義の現代は肉体よりむしろメンタルが疲れやすい。「できる」ことを求められ続けるのはしんどい。どのようにそこから逃れられるか?
興味深い一節があった。ある道があり、そこを目的地に向かって歩いている。駆け出したり走ったりしてもそれは違いにはならない。なぜなら直線を行くスピードが変わっているだけだから。道中をウロウロしたり、その場で踊ったりすることは違いになる。それは本来不要な行動で、目的地に向かうこととは別軸の動作を生み出しているから。
道草を楽しみ、踊るように趣味や仕事をしてる人を人生で何人か見てきた。そういう人たちはゴールすることではなく、自身のスキルの上達でもなく、ただその時間を楽しんでいるように見えた。他の人と比べて自分がどうだと考えることもなく、その人のペースで楽しんでいた。